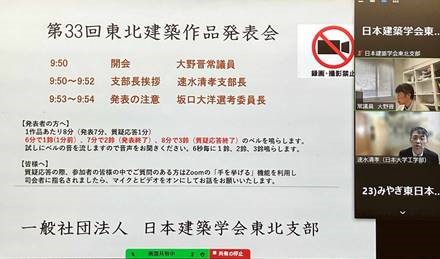開催レポート
建築文化考2024は、「自分らしさがひらくこれからの社会」というテーマで、シュリンクするまちにおける共助と個人の役割を探る場として開催された。都市や建築、そして社会の新たな在り方について考察を深めるこのシンポジウムシリーズは、日本建築学会による建築文化週間の中で行われ、今年で8回目を迎えた。合計224名(うち動画配信193名)と多くの参加者が集い、議論が交わされた。
議論の中心となったのは、近代社会が追求してきた効率性や利便性がもたらした快適な生活の一方で、社会的なつながりや共助が希薄化している現状への問いかけである。「自分らしさ」という個人の発露が、社会や地域との新しいつながりをどう再構築し得るのか、その可能性を探ることが今回の焦点となった。3名の登壇者各々の個人的な関心が社会的課題に結びついたプロセスに注目し、具体的な行動が結果として成果を挙げ、自身の取り組みが地域や都市の活性化にどのように寄与しているのかを語った。
最初の登壇者である栗生氏は、幼少期に神田祭りで見た、車道が人々の集う空間に変わる光景に感銘を受けたことを契機に、公共空間への関心を深めた経験を語った。その後、地域の記憶や文化を未来に引き継ぐ「町継ぎ」という活動を展開し、その中で、廃業した銭湯の部材を再利用した「銭湯山車」をうみだす。山車の巡行イベントを通じ、失われた地域の記憶を住民と共有し、つながりを再び生み出す取り組みを進めている。また、空き家や倉庫を地域住民が集まる場として改修し、現代におけるコミュニティの核となる空間の重要性を示した。
福井県若狭町で活動する時岡氏は、空き家をシェアオフィスや宿泊施設に改修し、地域再生を目指している。地域資源を活用した加工食品の開発や、観光資源としての「熊川トレイル」の整備を進め、地元住民との協働を通じて文化と自然を融合した持続可能な発展を模索している。また、若狭地方の課題を「課題先進地」として捉え、地域特有の文化や自然を生かした新しい価値創造の可能性を提起した。
島根県を拠点に「コミュニティナース」として活動する矢田氏は、住民の力を引き出し、それを地域全体の活力へとつなげる取り組みを紹介した。空き家だった元診療所を再生し、住民が自由に集まり得意なことを発揮できる「みんなのお家」を拠点に活動を展開したり、博労物件を活用し、その空間に内在するストーリーを活かした祭りを通じて地域の歴史や物語を掘り起こし、住民間の交流を促進する仕組みづくりを進めている。
後半のディスカッションでは、「舞台」と「居場所」という視点から地域社会の再生について議論が交わされた。時岡氏は住民が得意なことを発揮できる「舞台」の提供の重要性を訴え、矢田氏は空き家や旧公共施設を活用した「居場所」の創出が地域基盤を支える役割を果たすと強調した。栗生氏は、銭湯や喫茶店などが担ってきた「半公共的」な場所の価値を再評価し、地域住民の感覚や意識を引き出す新たな仕組みの必要性を提起した。
さらに、不完全さや余白が人々の助け合いや物語を生む可能性についても言及された。栗生氏は歴史的環境が持つ不完全さが人々の関係性を深めると指摘し、時岡氏は地方特有の課題を新たな価値創造の契機として捉える視点を示した。最後に矢田氏は、地方だけでなく都市部の人々の活力を引き出すことで、社会全体が支え合い輝ける未来を目指す重要性を述べた。
本シンポジウムを通じ、地域の力を引き出すためには「舞台」や「居場所」といった物理的かつ心の拠り所となる拠点を活用し、人々が自然に交流し、支え合う仕組みを構築する重要性が明らかになった。それぞれの取り組みは、地域が持つ歴史や物語を尊重しながら、新しい未来を形づくる可能性を示している。「自分らしさ」が自然に地域や社会とのつながりを再構築すること、そのプロセスは持続可能な社会の形成に向けた重要な手がかりとなるだろう。
[加藤詞史(加藤建築設計事務所主宰)、牛込具之(佐藤総合計画第1オフィスディレクター)]