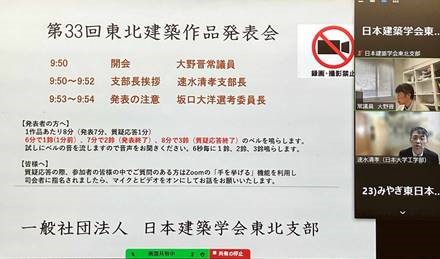第5回 地域再生・活性化の建築力
AR・VRを活用したまちづくり
まちづくりへのAR・VR活用のメリットとして、設計の質・効率の向上、PR力や集客力向上、安全・防災機能の強化、新たな体験の提供などが挙げられます。今回、古賀元也氏から、熊本市中心市街地を中心にIT技術を活用したまちづくり手法の提案と実践として、①車いすナビの開発、②防災マップづくり支援システムと災害イメージARアプリの開発、③メタバース商店街等についてご紹介いただきます。また、多米淑人氏からは、VRコンテンツとして現存しない福井城を高精細に再現した福井城復元アプリの開発、歴史理解の促進や観光資源として活用する取り組みについてご紹介いただきます。地域の活性化におけるIT技術の活用法や将来展望に対する考え方などをお聞きしたうえで、意見交換を行います。