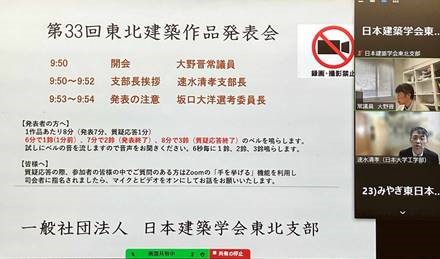開催レポート
「国家イベントについて考える」と題して、建築夜楽校が10月16日に開催された。
2025年開催を目指す大阪・関西万博は、税金の無駄遣いという観点から批判の声が上がっているが、一方で、開催すること自体の意義や経済効果の観点からの肯定的な議論もある。しかし、本質的に語られるべき議論は経済面の問題ではなく、そもそも万博とは何なのか、そしてそれが2025年においてどのような意味を持っているのかである。本イベントでは金銭的な観点からの大阪・関西万博批判ではなく、イベント資本主義と呼ばれ繰り返し行われる国家事業について、その問題の本質に迫った。
万博や五輪など、国家イベントに対する批評を発信され続けてきた布野修司氏(滋賀県立大学名誉教授)、イベント資本主義やメガイベントに対する論考を執筆/研究されてきた町村敬志氏(東京経済大学教授)、公共空間の設計を通して開かれた建築や都市を実践してこられた津川恵理氏(ALTEMY代表)の3名をゲストに呼び、建築会館ホールにてシンポジウムをおこなった。合計で338名(うち動画配信318名)の参加者があった。
会の前半には、布野氏と町村氏に本テーマにまつわる30分間のプレゼンテーションを行なっていただき、後半では講演いただいた内容を対象に3者による鼎談を実施した。
1956年生まれである町村氏は1970年万博当時の記憶が美化されたものとして、良いイメージとして定着していると述べる。その観点から人が集うというイベントには一定の意義があるとし、それが万博や五輪かはさておき、インターネットの時代にこそ祭りとしてのリアルなメガイベントと向き合うべきであると述べた。メガイベントの開催地を1900年から見ていくと最初は西欧列強帝国主義だったものが北米へ派遣が移り東アジアに移る。20世紀末1970以降からは万博はすでに時代遅れのイベントになっていたことが中止になった万博の数からよくわかる。それを延命させてきたのが現状である。93年ごろから日本政府とBIEが共同で万博を再構築するためのプロジェクトを開始、それを受けて愛知万博という話が具体化していく。その話を受けて1998年以後は万博が自然や環境を掲げるようになり、環境破壊の観点から中止するものがほぼなくなった。過去の万博が国のどの都市で開催されたかをみていくと一人当たりGDPが2割の国は権威の象徴として首都で開催する事例が多い。しかし6割や10割の国々は首都以外での開催が主流であった。しかし今世紀に入ってからどの国も再び首都で開催するようになる。
21世紀は一度先進国になった国が再びメガイベントを目指す、つまりGDPの低下によってさらに活性化するための集客手段として使われてきた。その結果、都心の再開発が進むと高度経済成長期にできたホールや劇場が潰れていく。メガイベントが普通のイベントの場を壊すという循環が起こるようなった。2025の大阪万博では1日15万人を集めないとならないが、これはすなわちその期間中毎日15万人集まる街を作るということである。ユニバーサルスタジオが1日5万人なのでその3倍。その視点から万博を捉えた時に、15万人の集積として、権威のためでも集客のためでも普通の場を壊すためのものでもない、よりよい形があるのではないか、町村氏のプレゼンテーションはそんな議題を提示してくださった。
布野氏のプレゼンテーションは万博を歴史的に紐解くことからスタートした。
明治以降日本の都市計画は万博開催のための施設整備を大きな開発手法としてきた。博覧会はもともと物産展としてスタートする。もとはフランスで行われていた世界各国の製品や芸術を物産展として紹介していただけであったが、それを国際的にしたのがロンドンでおこなわれた1851年の最初の万博である。最初は植民地の物産を本国で展示することから始まっていたのだ。それはすなわちどれだけ多くの植民地を獲得しているかという先進国同士の権威を示す場であり、またそれを契機に帝国主義的な権力を象徴するための近代的な都市開発をすることも目的化していたのだ。布野氏は日本も例外ではないという。明治期の政府主催の内国勧業博覧会は1877年から数回を上野で開催しその後、京都の岡崎公園で内国勧業博覧会を1895年に行なった。東京遷都したことの賠償金的に京都に金銭を支払い、博覧会との抱き合わせで京都の都市計画を実施したのだ。京都はその金でトラムを通すなどの都市改造を実施していく。
この時の万博=都市改造という流れは戦後も変わることなく、博覧会ブームが起こる。バブル期に重なりピークを迎える1986年に札幌博覧会以後、1986年から1991年までの間に実に61ヶ所で行われた。日本で行われた博覧会の中でも1番成功したとされているのが1981年の神戸のポートピアである。博覧会のために山を削って海を埋め、削った山で宅地造成する。一石三鳥と言われた万博であり、これは万博のためというよりは神戸の都市開発のために行われたに等しかった。万博に適しているから会場が選ばれたというよりも、あらかじめ決められた再開発戦略で立地が決められていたと布野氏は述べる。今回の関西大阪万博も同様にIR誘致や夢洲の開発をしたいという目的が主軸にあり、万博というのはそれを実行する理由づけにしかなっていないのではないかという問題提起をしていただいた。
その後、津川氏にも参加いただき町村氏、布野氏のプレゼンテーションを受けた鼎談を行なった。3者に共通した議論として、理想の未来の万博を模索すべきというものであった。身体的に人が集う状況をより肯定的に捉え、メガイベント自体を否定するのではなく、これからの時代に即したものに変えていこうというポジティブな議論である。
70年の大阪万博の際には施設の再利用を何も検討しておらず、残されたものは太陽の塔だけであった。その反省を活かし、会場計画の時から施設の再利用を検討するような仕掛けがあれば変わるのではないかという提案も飛び出した。また2024年のパリ五輪では新しい施設を3つしか建てなかったが、既存施設を使うという提案を日本社会は積極的にしていくべきだという話も上がった。
日本は世界に類を見ない鉄道大国である。その交通インフラを、会場を構成する要素として使うことはできないのだろうか。大阪駅の1日の乗降客数は35万人程度であるが、それは町村氏の議論の際に登場した、2025年万博が目指している1日の来場者数15万人を大きく上回る。単純にこれを合算することはできないが、この鉄道ネットワークを会期中に存分に利用して、会場を点在させるという案である。大阪・関西万博と謳われながらも、会場は大阪だけで神戸や京都は会場とは無関係である。明かにIR誘致、夢洲エリアの再開発のためだけに選定された土地を使うのではなく、関西全域を交通インフラを主軸としたネットワークで結ぶような万博のあり方も提案された。
これからのメガイベントのあり方について、批判的ながらも前向きな意見が飛び出し、非常に有意義な会となった。
[山本至/itaru/taku/COL.共同主宰]