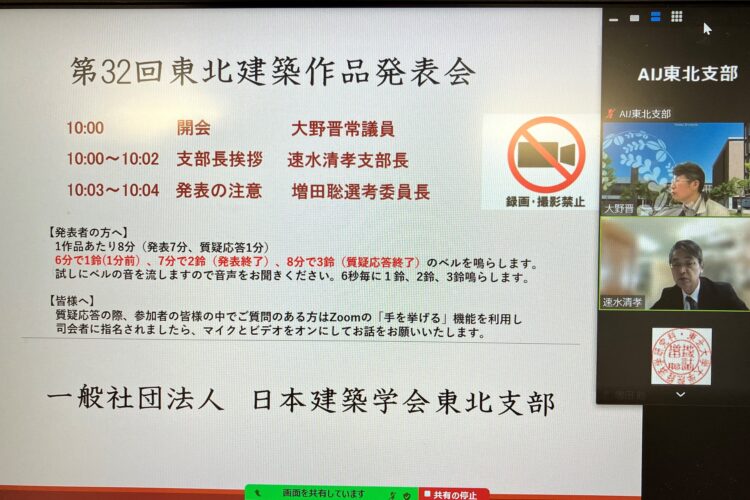開催レポート
都市をテーマにしてシンポジウムを重ねてきた建築文化考。今回は一度「都市」の外側に出て、距離的、時間的に遠ざかり、都市を俯瞰することで新たな視点を得る機会とすることが必要ではないかと考えた。そこで「遠ざかる都市─現在進行形都市のオルタナティブをさぐる」をテーマとし、10月30日(月)に建築会館ホールおよびZOOMによるリアルタイム動画配信にて開催した。参加者は計100名(うち動画配信71名)であった。
パネリストには、安宅和人氏(慶應義塾大学教授/LINEヤフーシニアストラテジスト)、石川直樹氏(写真家)、佐藤洋一氏(早稲田大学教授)の3名を招き、シンポジウムの前段にそれぞれのプレゼンテーションを行い、後段にディスカッションを行った。
石川直樹氏は、帰国したばかりのヒマラヤから、東京へと「高度」をキーワードに、登頂を目前に自身の身に迫った生死、雪崩に挟まれるなどのリアルな体験を交えて語った。極地に向かう過程で通る都市や村からベースキャンプへ、徐々に人が暮らせない山へと至る道程を「グラデーション」として、人の生活圏から人が生活することの不可能な超高所までを踏破し、つぶさに写真を撮り続けることの身体性と価値を共有した。また、コロナ禍の2年間は、人の消えた渋谷で「ねずみ」を追い、ねずみの視点から(インスタント・フィルムカメラで)撮影を重ねたという。ねずみを起点として都市を探っていくと、石川氏の故郷である渋谷とは異なる渋谷が立ち上がってくる、そんな感覚を浮き彫りにしつつ、東京は無色透明の都市であり、思い出をつくろうにも街の姿が変わり消えていくことを示した。また、人工的物で埋められた渋谷で、地表を這い生き延びるネズミの生命力を浮かび上がらせ、都市から辺境まで、日常も非日常も区別なく、自分の体が反応したものを撮り続けるなかで見え隠れする生命を通して、都市の意味を対極の高度へと至る道程に、同じ地平として示した。
佐藤洋一氏は、戦後日本のカラーフィルムを国内外で発掘していくことを通し、また、自らの身体を使うことで、かつてのフィルム写真に映し出された都市空間を現在へと引き寄せることの意義を語った。佐藤氏は戦後の都市空間を探るべく、アメリカ国内を車で4万キロ移動し、当時、進駐軍などで訪日した個人が撮影したパーソナルなフィルムをアーカイブス機関などで確認、収集した。題材とした京都の写真記録(衣川太一氏と共同)を地図上にプロットし、同じ画角のレンズをつけたカメラで撮影者と同じ視点の位置獲得に執念を燃やす。八坂神社の狛犬の写真では、西楼門の階段脇に腰を下ろして撮影していたことを突き止め、かつての撮影者の身体を通して過去とつながる追体験を重視し、価値化を図った。一見、分断された単写真を撮影者の移動を推定しながら整理しつなぐことで、都市空間の理解が明らかに変化し、かつての都市空間に近づく「身体知」に出会うこととなると結んだ。写真に残された断片化された情報に対して、身体を媒介させることで実空間の価値を再編集している。
安宅和人氏は、今回のセッションのテーマである遠ざかる都市に対して、自身の活動が都市から遠ざかるという立ち位置であると示したうえで、「風の谷」運動論について語った。集落の美しい「疎」な空間をあげ、そこかしこにあることの魅力と価値、世界中にあるその場所が無人化していくことを課題として提示する。一方、人口はここ200年間で爆増しており、これら自然豊かな環境を、新しいテクノロジーの力を借りてサスティナブルな空間にできないかという試みを「風の谷」と名付け自らのアクションとしている。同時に地球上の人類が抱えている諸課題についても投げかけを行った。20年前はテロリズムであったが、現在は「地球との共存化」へのシフトであると説く。噴火災害などに対しての本会のスタンスを会場へ鋭く問いかけ、温暖化による熱波や山火事の多発、シベリアの永久凍土地帯の融解に伴う場所の変化、さらに新たなパンデミックの出現といった未来を力強く語り、パンデミックレディ、ディザスターレディであること、「地球との共存」が人類の問題であることを共有した。都市部においても「開でありかつ疎」である空間への刷新を論じ、温暖化、自然災害などの事象に対しては、官だけではなく民(企業も個人)もディザスターレディ化が必要であると締めくくった。

二部のディスカッションでは、三者のカメラや写真に対する共通の興味をベースとしながら、「極地と対極の都市での順応について」「都市における時間軸の断絶について」「ヴァナキュラーな知恵を活かす」といった広がりのあるレンジのなかで、まさに都市のオルタナティブを探る議論が展開した。
石川氏は、山岳地帯においても都市部においても周囲の環境に対して、自分を変えていくことを実感をもって語り、極地あるいは自宅でも、その場所へ順応していく自らの生き様を示すなかで、都市から極地へのさまざまなグラデーション、生きる術を説き、周りを変えることだけではない自分を適応させることの意味を問いかけた。
佐藤氏は、日本におけるカラーと白黒の写真に内在するイメージについて、戦前からカラー写真はあるものの戦中・占領期に歴史的な「断絶」があること、一方、アメリカでは写真文化は停滞することなく、アーカイブス化などの底支えがされており、その意識の構え方の違いを述べ、写真を通して都市・文化との距離を課題とした。
安宅氏は、断絶と再生を繰り返す、スクラップアンドビルド的な日本の都市像に対して、特に東京は災害に対する対応を重ねてきた結果、美しく整っていない街を形成していると述べる。その状況を示しながら、街の読解には短歌のように間合いを読む必要があると語り、断片から読み解く必要があることの難解さを示し共有した。併せて、場所の記憶を残し、次につなげるバトンを考えることの必要性を説く。さらにヴァナキュラーという発想、疎空間においてのディザスターレディの視点から、ヴァナキュラー的なものづくりを内包しておくことで、復旧力が桁違いに上がることなどを提案し、石川氏の言う「シェルパ族のもつブリコラージュ的な知恵や技術」に希望を共有した。
この地球や空間あるいは街が個人のものではなく全員の持ちものであり、しかも次の世代、その次の子どもたちのものでもあり、かつ人類だけのものではないという意味での「コモン(コモンズ)」を共有し、最後に3人の登壇者の考えが交差することになった。それは「身体知」を活かして来るべき未来に備えていくことであり、その視点にオルタナティブな都市を生き抜く希望の光を垣間見た。
[加藤詞史/加藤建築設計事務所主宰
牛込具之/佐藤総合計画第1オフィスシニアアーキテクト]