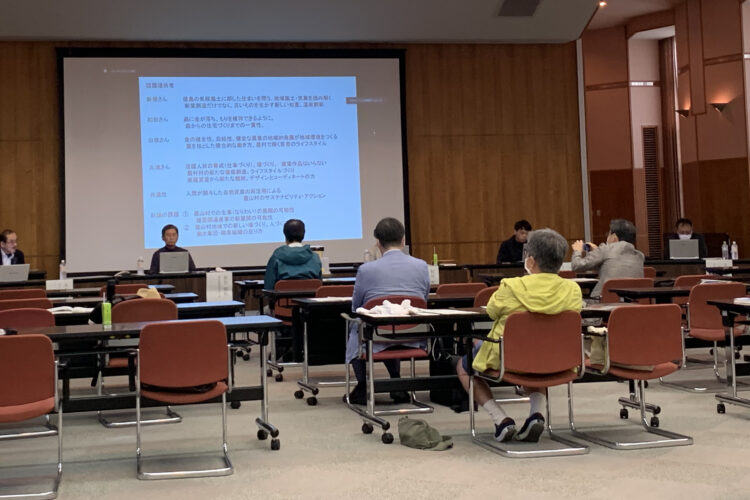アーカイブ(YouTube)
VIDEO
開催レポート
今、なぜ都市のテクスチュアなのか。近代建築の勃興期である100年前、スペイン風邪などのパンデミックとともに、建築や都市には「結核菌だらけの古臭いかくれ場所からの脱却」「自然材料を人工材料に入れ替えること」(ル・コルビュジエの言葉)などが求められ、結果としてツルツルピカピカのテクスチュアが今日の都市体験を生み出してきた。
新たなパンデミックを経た今、都市を形づくる「テクスチュア」はどこへ向かうのであろうか。第6回となる今回は「都市のテクスチュア─眼で触れる都市像をさぐる」と題して、その背景をモデレーター・加藤詞史が冒頭に解説した。10月13日(木)に建築会館ホールおよびYouTubeによるリアルタイム動画配信にて開催し、参加者は計248名(うち動画配信236名)であった。パネリストに、港千尋氏(多摩美術大学教授)、野老朝雄氏(美術家)、平瀬有人氏(佐賀大学准教授)の3名を招き、登壇者の実践を踏まえたディスカッションを行った。
美術家である野老氏は、街にある記憶と多様な時間が混在した状態、一見バラバラで様々なエレメントの背景にある「個/群/律」から話を始めた。実例として、ドットパターンを例に、個々のドットとそれらが群をなす背景にある補助線としての律(ルール)、その律が「紋様」を生み出すという一連の関係性を提示した。さらに、その律のあり様によって「ゆらぎ」などの現象を発生させることなどの実践を説明した。自身の創作のスタンスである「律」とは、言い換えれば、LET【 】RULEの【 】に従わせるという概念であるとし、創作における「縛り」がもつ、(逆説的ではあるが)自由さや救いについて触れつつ、氏が創造するパターンや、律を内包する立体造形が「つながり合う」ことの意味や大切さを問いた。作品を通して、「個と群と律」が、他者や空間へとつながり社会へ働きかけることの可能性について語った。
野老朝雄氏
建築家・平瀬氏は、「frame / material memory」と題して解説した。現代の建築都市空間を再価値化するためには新しい視点の獲得が必要であり、そのためには「frame」という概念が重要であると説く。小津安二郎やカルロ・スカルパを例に挙げながら、空間をフレーミングすることで、次の空間への「予兆」を促すことができ、フレームを複数重ね合わせることによる時間を空間に内包させることの可能性を提示した。もうひとつの概念「materialmemory」は、時間の経過した建築材料は履歴や時間を内包しており、ひいては、歴史との接続や周囲の豊かなネットワークに組み込まれていることへの着眼を共有した。実践例として、かつての九州大学の寮を「素材」としてスポリア(建築の部位を転用する行為)し、「採取(生けどり)」した解像度の高い「記憶が宿る」ヴォリュームと、解像度の低い「空虚なヴォイド」としての未来を予兆させるフレームを並置させることで、都市との新たなつながりを生みだす試みを解説した。強い造形が受け入れづらい社会に対して、それでもなおシンボル性を示すこと、力強いイメージを定着させることが、都市のテクスチュアを考えるうえで重要であると語った。
平瀬有人氏
「群衆」を写真とテキストによる表現の原点とした港氏は、本テーマの前提として、「イ会場風景 ンフラグラム化」の概念を提示した。写真時代以降の撮影行為がインフラ化され、人間が社会を記録する時代から、人がカメラに制御される=世界が人間をフレーミングする時代への転換点にあると指摘する。
一方で、都市の生命力(VITAL)を支えるものはVISTA(眺望)とVOID(ヴォイド)であると語った。眺望は、自らの立ち位置を明確化し、ヴォイドは、都市のヴァイタリティを充填する場である。2つの関係が都市を都市たらしめていると説く。さらに、テクスチュアとは「編むこと」が起源であることに言及し、アーティストであるイグシャーン・アダムスが制作したタペストリーが、建築の表層にこびりついたシミや痕跡を観察し、テクスチュアをつくりだしていると解説した。そこには都市に対するアーティストのレスポンスがあると指摘する。翻って、コロナ禍が始まった2020年以降の都市文明とは、一度立ち止まり、離れてみること、ともに過去を想起し未来をみるという視点が大事であると締めくくった。
港千尋氏
後段では、野老氏がもつ都市を捉える視点に平瀬氏が応答し、港氏によって言説化されるという幸せな時間が流れた。「後ろに下がりながら100年後に向けて投げる」と港・野老両氏は共有する。終盤、港氏による野老・平瀬両氏の実践に対する気づきが、都市のテクスチュアを本質へと収斂させた。世界に眠るパターンをいかに紋様へと転換し(律を見出し)、建築に取り込むか。その一つに太陽の光を用いること、まさに影である。写真とは影を留める技術であり、建築との関係においてチャレンジングでエキサイティングな時代になるのではと語る。
現在の社会情勢においても、影とはエネルギーとの相関であり、様々な危機が目の前にあるなかで、光の建築の時代から影の時代へ、危機を価値へと転換することで新たな時代のテクスチュアへと接続しうるという、可能性に富んだシンポジウムとなった。
[加藤詞史/加藤建築設計事務所主宰